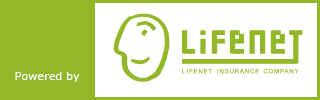文章を書くことは仕事の基本。特に「わかりやすく」「伝わる」ように書くことは、無用な誤解を避け、仕事を円滑に進めることにも役立ちます。
文章を書くことは仕事の基本。特に「わかりやすく」「伝わる」ように書くことは、無用な誤解を避け、仕事を円滑に進めることにも役立ちます。
もちろん、ビジネスシーン以外でも、ブログやSNSなど、自分の意図が「伝わる」ように書くことは、ネット時代の今、多くの人にとって重要になっています。では、どう書くべきなのか?
「伝える」ための文書術には、たくさんのコツがありますが、実は、次の2点を抑えておくだけでも、かなり文章の意図はわかりやすくなります。
それは『日本語の作文技術』(著・本多勝一)という本にまとめられているコツ。同書は書名の通り、日本語で文章を書くうえでの「技術」を説いた名著として知られ、刊行から30年以上が経った今も、学生からビジネスパーソンまで、あらゆる世代の人に読まれています。
今回紹介する「コツ」は、読点の打ち方。誰もが文章で使う「、(テン)」のことです。
■「テン」がないために事実が誤解される
しかし、読点の打ち方ひとつで、そんなに文章が変わるものなのか――。そういう疑問に、著者はこう答えています。
、(テン)や。(マル)や「(カギ)のような符号は、わかりやすい文章を書く上でたいへん重要な役割を占めている。とくにこの場合、論理的に正確な文章という意味でのわかりやすさと深い関係をもつ。
ここで重要なのは、『日本語の作文技術』で述べられていることは、決して「詩的な」「美しい」文章を書くためのコツではないということ。あくまで「論理的な」文章を書くための技術の紹介に徹しているからこそ、実用的な書として、ロングセラーになったのです。
そして、「論理的な」文章を考えるうえでは、マルやテンが非常に大切であると、著者は言います。具体例で説明しましょう。
渡辺刑事は血まみれになって逃げ出した賊を追いかけた。
この文章には「わかりにくい」ところがあります。それは「血まみれ」になったのが、「渡辺刑事」なのか「賊」なのか、この文章からは判断ができないところです。ここにはテンが足りません。
渡辺刑事は、血まみれになって逃げ出した賊を追いかけた。
こうするだけで、血まみれになったのが「賊」のほうだとわかります。反対に「渡辺刑事」が血まみれになっていた場合は、
渡辺刑事は血まみれになって、逃げ出した賊を追いかけた。
とテンを打ちます。文章の全体をいじらなくても、テンを打つだけでこのように意味が変わるのです。
これを著者の本多氏は読点の「第1の原則」として、「長い修飾語が2つ以上あるとき、その境界にテンをうつ」と説明します。
先の文例でいうと、「追いかけた」という述語に、「渡辺刑事は」「血まみれになって逃げ出した賊を」という2つの修飾語がかかっています。なので、その境界線にテンを打てば、「血まみれになって」という言葉が、事実とは反対の意味に誤解されることがなくなるのです。
■「テン」は強調にも使える
もうひとつの読点の原則が、「語順が逆順の場合にテンを打つ」というものです。
やはりあいつか、下山総裁を殺したのは。
これは「下山総裁を殺したのはやはりあいつか」という文章の語順を逆にしたものです。わかりやすくするために、逆にした境界線にテンが打たれています。ここには文章としての読みやすさのほか、「強調」という意図も表れています。
このようなケースはすぐに理解ができると思いますが、次の文例ではどうでしょう。
Aが私がふるえるほど大嫌いなBを私の親友のCに紹介した。
パッと見で読みづらいですね。これは本来、
私がふるえるほど大嫌いなBを私の親友のCにAが紹介した。
という文章です。しかし、この文章の書き手は「Aが紹介した」事実をより「強調」して伝えたかったので、「Aが」を逆順にしてアタマに持ってきました。ただ、テンがないために、その意図がわかりづらくなっているのです。そこで、第2の原則に従うと、
Aが、私がふるえるほど大嫌いなBを私の親友のCに紹介した。
とテンを打ちます。これが第2の原則です。
■ルールではない「テン」もある?
以上が読点における2大原則ですが、これ以外のルールで使われているテンを目にすることもあるでしょう。例えば、
(1)しかし、彼女は我慢した。
(2)父は、死んだ。
(1)は接続詞のあとにテンを打っており、いかにも文章のルールに見えます。しかし著者によれば、これは「自由なテン」なのです。「しかし彼女は我慢した」と書いても、文章としては問題ありません。
これは(2)もそうです。「父は死んだ」と書いても事実は変わりません。では、このテンはなんのために打つのか。
それは「思想の表現」です。もう少し言い換えれば、「書き手の表現の意図」によってテンが打たれています。
(1)であれば、前段の文章を受けて、「しかし」という逆説を強調したい場合。(2)であれば、「父が、死んだ」と書いたほうが、より哀切な感情が付託されています。
ただ、これは表現上の問題であって、「論理的な」文章術という意味では、読点のルールなわけではありません。書き手の意図によって、テンを打ったり打たなかったりして良いのです。
『日本語の作文技術』には、このほかにも「伝わる日本語」を書くうえでの基本的で、しかも大切なコツがたくさん紹介されています。文章の書き方に悩んだときに、何度でも読み返しておくべき1冊といえるでしょう。

『日本語の作文技術』(朝日新聞出版)
<クレジット>
文/小山田裕哉