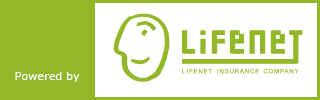写真左:東京ベイ・浦安市川医療センター救急科 溝辺倫子先生、右:同センター長補佐・救急科部長 志賀隆先生
「医療を通じ地域の絆を育みます。」との理念を掲げ、日本の最前線で医療に取り組む病院があります。2012年に新病棟がオープンし、現在では24時間365日、常に10名以上の医師が勤務する救急体制を敷いている東京ベイ・浦安市川医療センターです。アメリカで医療と経営等を学び、質の高い救急体制と総合力のある救急医の育成に尽力する救急科部長・志賀隆先生、同院で救急医として勤務する溝辺倫子先生に救急医療現場の実態についてお話をうかがいました。
■オープンな病院を作りたい
──志賀先生はアメリカで学ばれたとお聞きしています。東京ベイ・浦安市川医療センターの救急科部長に就任されるまでの歩みを教えてください。

志賀:総合診療に魅力を感じていたので、大学卒業後、まず東京医療センターで最初の研修をしましたが、アメリカには大学時代からずっと行きたいと思っていたんですね。そこで、沖縄の米国海軍病院で研修を受け、その後浦添総合病院に2年間勤務し、ドクターヘリで離島の医療にも貢献しながら、アメリカの救急研修プログラムのマッチングに応募しました。
その結果、アメリカでは常にトップクラスにランクされているミネソタのメイヨークリニックに決まり、そこで3年勤務した後、ハーバード大学マサチューセッツ総合病院の救急外来で指導医として働きました。
ハーバードでは働きながら大学院で公衆衛生修士を取得しました。その中で、臨床の研究や医療のコミュニケーション、マネジメント、医療経済について学びました。帰国したのが2011年。この病院の立ち上げにお声がけいただき、現在に至ります。
──異色の経歴ですね。病院の立ち上げに携わるにあたって、どのような点に留意されたのでしょう?
志賀:以前よりは少なくなりましたが、日本の病院は学閥で左右される世界です。出身大学が重視されるんですね。しかし、そうしたことは患者さんにとっては何の意味もない。そこで、当院では学閥でまとまらないように、内科の隣は小児科、麻酔科といった具合にランダムに机を配置しています。
初期研修医だけはまとまって机が配置されていますが、あとはばらばら。患者さんが運ばれてくれば、臨機応変に他の科の医師が入り、チームを編成してスピーディに対応しています。
──個室もないんですね。オープンなレイアウトに驚きました。
志賀:すべて共用スペースにしていて、カンファレンスのスペースも共用です。だから話しやすいんですね。この前の患者はどうだったの? と医師同士が気軽に話せる。精神的距離は物理的距離に比例しますからね。すぐ隣に小児科の先生がいると自分の子どもの話や小児科の話になる。近いのは良いことですよ。

医師たちのデスクはブースで仕切られているだけで、役職者も個室はない
■巨人の背中に乗って広い世界を見た方がいい
──なぜこのような体制の病院で、救急部門を作ろうと思われたのですか?
志賀:これまで働いてきた病院にはそれぞれ良いところも悪いところもあって、いつか理想の病院や理想の部門を作りたいと考えていました。一から自分が立ち上げて、良い先生を集めて、良い病院を作りたかった。その原動力になっているのは、うまくいっていない医師同士のやりとりによって患者さんが不利益を被る現場を見てきたからです。
これが患者さんのためになるのかという気持ちがあった。そうした悲しい経験や悔しい体験を踏まえて、自分ひとりの力ではなく、外の世界にある、より良いものを応用していこうと考えました。巨人の背中に乗って広い世界を見た方がいいじゃないですか。研究や科学はそうあるべきだと思います。
──溝辺先生もそうした志賀先生の理念に共鳴されて参加された?

溝辺:はい。私はもともと、体を部分ではなく全体でみたいと思っていたのですが、研修を経て地元に近い徳島の病院で、何か専門をもとうと循環器内科医として働いていたとき、やっぱり体全体をみたい、と思うようになりました。そんなときに、浦添での研修時代にご一緒した志賀先生が救急部門を立ち上げたと聞き、2年目に後期研修医として入りました。
本来なら医師8年目で研修の時期ではないんですが、融通して救急科に受け入れていただきました。ここでは、患者さんの利益を第一に考えて、みなで知恵を持ち寄って相談してチーム医療が円滑に行われていると思います。
──チーム医療がうまく機能している例はありますか?
溝辺:例えば、嘔吐が続いている患者さんが来院されたら、内科がまず診て、腸閉塞が原因だとわかったらその日のうちに外科で手術ができます。ひとりの医者でできないことでも、複数の医者が集中的に関わることで早く診断して早く治療ができるんですね。ほかの病院だと何曜日にならないと何々科の先生に診てもらえないということがよくありますが、ここはそれがない。電話1本で対応してくれることがほとんどです。
志賀:もちろん、うまくいかないこともありますが、その場合には必ず検証をしています。当事者の問題なのか、機器の問題、システムの問題なのかなど。検証して対策をとる。それが重要ですね。

集中治療室にて。ここでも臨機応変に他の科の医師が入ってチームが編成される
──年間に受け入れる救急車の台数が多く、救急車の応需率は非常に高いとお聞きしました。
志賀:1年に8300台の救急車を迎え、救急車応需率は96%にのぼっています。県内トップクラスの救急部門に成長しました。
■救急医療の現場における、就業不能の実態
──救急医療の現場では、突然の病気や事故で就業不能に陥ってしまった患者さんもご覧になっていますか?
志賀:強く記憶に残っているのは、20代の男性の患者さんの例です。仕事は確か建設業でした。結婚していて、すでにお子さんがいる方でしたが、スクーターに乗って帰宅している途中で交通事故に遭い、右肩がほとんど切れかけていました。すぐ外科の先生につないでもらいましたが、脳出血もしていた。
結局、半身不随になって最終的にはリハビリ病院に行かれました。仕事をしていくのはもう難しい。入院も長かったですね。たしか4ヶ月くらい入院されていたと思います。奥さまは明るく前向きな方でしたが、小さなお子さんを抱えていて、これからどうやって生計を立てていかれるのだろうかと。大変だったと思います。
もうひとつは、くも膜下出血になられた例です。ある社長さんが、突然の頭の痛みで運ばれてきて、検査をした所、くも膜下出血だと判明。手術は無事成功したのですが、しばらく後遺症が残ってしまいます。退院されてからも、普通に会話をすることはできても、高度に頭を使うような仕事はなかなか難しいですから、その会社の社長を退職されたと聞きました。
──当社の就業不能保険の加入者には医師の方が多いのですが、やはり日頃そうした病気や事故で長期に働けなくなる方に触れていると、そのリスクを考えるようになる、ということなのでしょうか。
志賀:そういう面もあるかもしれませんね。就業不能という悲しいケースを目の当たりにしているという。それから、そういった保険があるという情報をもっている医療従事者が多いのかもしれません。
──医療従事者から見て、今後、保険会社が患者さんために検討していくとよいと思うことは何だと思われますか?
志賀:患者さんが保険に加入されていた場合、保険会社が患者さんの代わりに、直接病院へ医療費を支払うことができるようになったら、患者さんの負担も減るのではないでしょうか。いろいろと超えるべきハードルはあると思いますが。病院からすると、未収金というのは大きな問題ですので、もし保険会社が先に立て替えをしてくれるのであれば病院も助かるのかもしれません。
溝辺:加入者の方に、ヘルスケアなどのプログラムを提供するのは喜ばれそうです。例えば、食事の宅配やフィットネスといったサービスを選べて、契約者なら安く利用できたり会員になれたりする。そんな選択肢があってもいいように思います。
──いろいろな方法が考えられそうですね。ありがとうございました。
ライフネット生命の販売する就業不能リスクに備える保険はこちら
<クレジット>
取材/ライフネットジャーナル オンライン編集部
文/三田村蕗子
撮影/植松千波