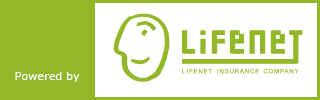『「本」をつくるという仕事』稲泉連 (著)、筑摩書房
無類の読書好きで知られるライフネット生命会長 出口治明は、趣味が高じて書評を連載しています。「オルタナティブ・ブログ」に掲載した書評の中から、「本」がつくられるまでの過程を慈愛深く描き出した『「本」をつくるという仕事』についてご紹介します。
自分で本を書くようになってから、1冊の本が世に出るまでには本当にたくさんの人のお世話になっていることがよく分かった。本書は、「書店は広大な読者の海と川とがつながる汽水域であり」、本づくりとは「源流の岩からしみ出た水が小さな流れとなって集まり、次第に1本の川に成長して海に流れ込む」ようなものだと考える著者が、8つの目的地を求めて川上へと遡っていく物語である。
最初は活字書体。見出しは大声、本文は静かな声。確かに、と合点がいく。秀英体という伝統ある書体を7年の歳月をかけて改刻するプロセスが達意の文章で綴られる。書道の「永字八法」のように全ての基本として試作される文字は「国東愛永袋霊酬今力鷹三鬱」の12字で、力などのシンプルな字の方が難しいそうだ。100年後も使われることを目指して大改刻が行われたが、行く末を見届けられる開発メンバーは無論ひとりもいないのだ。
製本、活版印刷と続いて校閲。僕は何冊か歴史の本を出しているが、校閲の方がしっかりと見てくださるので本当にありがたく思っている。新潮社の創業者は校正者でもあった。そこで校閲部門を大事にして採用時も編集部門と校閲部門で試験が分かれていたという。著者は新潮社の伝説の校閲者を訪ねる。校閲とは、原稿を送り出す側にいる編集者と読者の側に立って原稿を読む校閲者の「ゲラを通した闘い」だ。したがって、校閲は出版社の価値であり、良心である。著者はこうした「校閲哲学」がどのように培われたのか校閲一筋40年のプロの軌跡を追っていく。面白い。そして生き方が本当に素敵だ。何しろ良い校閲者になる方法が「酒を飲みに行きなさい」なのだから。あらゆる道の達人が、豊かな人間性を備えていることが実感される。
そして紙。酸性紙から中性紙へと転換するプロジェクトの顛末が語られる。試作をやり直すこと3年、ついに成功したとき「おお」というどよめきが起こった。よい紙とは何かを求めて技術の力が過去を乗り越えていく。
次は装幀。夏目漱石は細やかな遊び心を持つ装幀家でもあった。僕は、書店に行って美しい本に出合う都度、中身を読む前から気持ちがとても温かくなり嬉しくなる。著者が訪ねたブックデザイナーは「本が旦那、装幀家は芸者」だという。「嫌いな相手でも、その前で芸者は踊らなあかん」、なるほど。しかし根底に流れるのは、「『美しい本』への憧憬は人間が持ち続けるものであるはずだ」という固い信念である。だからこそ、「本をデザインする仕事への熱意もわいてくるのだ、と」。「やっぱり紙の本が美しくなければあかんのですよ」というデザイナーの言葉に、喝采を送りたくなるのは僕だけだろうか。
海外の本の架け橋となるエージェント、子どもの本を書く大人を訪ねて著者の豊潤な川上への旅は終わる。仕事に対してとことん向き合おうとするプロの矜持がひしひしと伝わってきた。本が好きなみなさんには、ぜひとも紐解いて欲しい1冊だ。