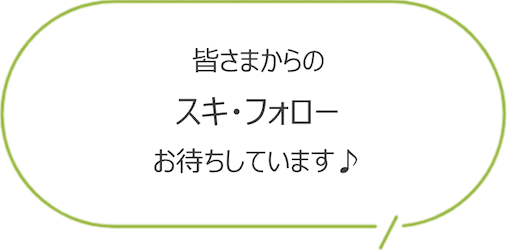病気やケガで働けない時に申請を!傷病手当金に注目!
社会保険労務士(社労士)でもあるファイナンシャル・プランナーの中村薫先生の「だれも教えてくれなかった社会保障」シリーズ。病気やケガで休職せざるを得ないときに使える「傷病手当金」、ご存じですか?
中村先生いわく、「日常的に使うものではないので、意外と知らない人が多い」のだとか。基本のポイントを教えてもらいましょう!
【今回のポイント】
・傷病手当金は病気休業中のための制度です
・有給休暇と傷病手当金どちらを使うか迷ったら、担当部署に相談を
・傷病手当金を受け取るには、加入している健康保険に申請を
傷病手当金ってなに?
傷病手当金とは、病気休業中で通常よりも給与が少ない時のための公的な制度です。対象となるのは、基本的には会社員や公務員の方です。長い間会社を休まなければいけないときに、生活を支えるお金を受け取ることができます。これを知っていれば、安心して仕事を休んで治療や療養にのぞめるはずです。
さらっと一通り頭に入れておき、もしものときに思い出して活用してください。ただし、受け取るには条件があります。簡単に、一つずつ説明していきますね。
※この記事に掲載したケース以外にも、国や自治体が認めた場合に、特別に傷病手当金が受け取れることもあります。
※ここでは制度の概要を説明しています。詳しくは加入している健康保険、勤務先の担当部署などにご確認ください。
※専門的な用語をできるだけわかりやすい用語に置き換えています。また、詳細な説明を省略しているため、すべての要件まで触れていません。最新の情報は、各健康保険のウェブサイトにてご確認ください。
①プライベートでの病気やケガであること
傷病手当金の対象となる休業の原因は、業務外の「病気」または「ケガ」です。業務上の病気やケガ、通勤途中のケガなどは、労災保険の対象であり、傷病手当金の対象とはなりません。
また、自己判断で休業するのではなく、「仕事に就くことができない」ことを医師に証明してもらう必要があります(ただし、医師の指示であれば、自宅療養も傷病手当金の対象となることは、覚えておいてくださいね)。
②まず3日間連続して休むと、その後の休みから給付がスタート

傷病手当金は、3日間連続で会社を休んでいることが条件となっています。その条件を満たしたうえで、4日目から傷病手当金が支給されるのです。
そのため、同じ10日間のうち「3日間出勤して、7日間休業した」というケースでも、傷病手当金が支給される場合と、されない場合があります。下に示した図表1のうち、ケース3の場合は傷病手当金が支給されません。
3日間連続で休んだ後は、飛び石の休みでも対象になります。(図表1のケース1、2)
図表1 傷病手当金の支給の例

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から通算で最長1年6ヶ月(令和2年7月2日以降に支給開始されたもの)です。休業が長引きそうなときも、ある程度心強いと思います。
③過去1年の月給の平均から1日の給付額が計算される
傷病手当金の1日あたりの給付額は、ざっくり言うと1日のお給料の3分の2です。
過去1年分の標準報酬月額(健康保険の保険料を決める元になる額)を平均して計算します。
過去12ヶ月の標準報酬月額の平均額÷30×2/3=1日あたりの金額
なお、傷病手当金は、働いている本人が休業したときに、一定額を限度に穴埋めするものなので、扶養家族が病気等で入院や療養をした場合は対象となりません。
また、以下のようなケースも注意してください。
・休業中であっても、給与が3分の2以上出ている場合は受け取れない
・給与が3分の2より少ない場合は、給与との差額を受け取れる
会社を休むのなら、有給休暇と傷病手当金どちらを使う方が良い?

病気やケガ等で休業する必要があっても、それほど長引かない場合は、有給休暇を使うか、傷病手当金を使うか悩むところです。
有給休暇であれば、原則として就業規則で規定された1日分全額が支給されますが、傷病手当金は1日分のおよそ3分の2の金額です。
ただし、有給休暇は本来の出勤日に休んだ場合に、その日労働して得られる分を受け取れるというものです。
一方、傷病手当金は土日祝日の休業も含めて1日として計算され、支給の対象となります。
どちらが良いかはケースバイケースです。会社の総務など、担当部署に相談して決めると良いでしょう。
※健康保険組合によっては1日の3分の2ではなく、さらに上乗せして手当を受け取れる場合があります。健康保険組合に加入している方は上乗せ後の受給額を確認してから判断してください。
その他、有給休暇を使い切ってしまうと復職後に困るため、傷病手当金を受給するという考え方もあるでしょう。
また、傷病手当金を受給するには医師や会社から書面を受け取るといった手続きが必要ですから、その点も考慮してみてください。
傷病手当金を受け取るには、どこで誰が手続きするの?
傷病手当金は、自分で加入している健康保険に申請します(会社が申請してくれることもあります)。
お持ちの健康保険証に「全国健康保険協会 〇〇支部」や「〇〇健康保険組合」といった文字があれば、それが申請先です。
各健康保険のウェブサイトから書類をダウンロードできることもあります。ウェブサイトを見るか、電話などで申請のポイントなどを確認すると良いでしょう。
例えば「全国健康保険協会(協会けんぽ)」では、書類をウェブサイトからダウンロードでき、申請は郵便でOKです。
自営業者は基本的に傷病手当金がありません
ここまでは会社員や公務員で健康保険に加入している人の説明でした。
実は、自営業者やフリーランスで働いている人などが加入する国民健康保険には、基本的にこの制度がありません。最新の情報は各自治体のウェブサイトで確認してください。
<関連記事>
<クレジット>
●なごみFP・社労士事務所 中村薫
<プロフィール>
中村薫(なかむら・かおる)1990年より都内の信用金庫に勤務。退職後数ヶ月間米国に留学し、航空機操縦士(パイロット)ライセンスを取得。訓練中に腰を痛め米国で病院へ行き、帰国後日本の保険会社から保険金を受け取る。この経験から保険の有用性を感じ1993年に大手生命保険会社の営業職員となり、1995年より損害保険の代理店業務を開始。1996年にAFP、翌年にCFP®を取得し、1997年にFPとして独立開業。2015年に社会保険労務士業務開始。キャリア・コンサルタント、終活カウンセラー、宅地建物取引士の有資格者でもある。
※こちらの記事は、ライフネット生命のオウンドメディアに過去掲載されていたものの再掲です。