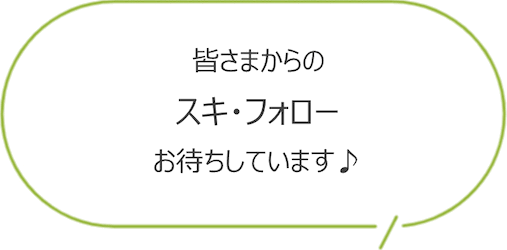子どもの進路希望をかなえるため、教育費をどう準備すべき?【FP黒田の人生相談】
子どもの進路と教育費は保護者にとって気がかりな問題です。子どもの希望をかなえてあげたいとは思うけれど、先立つものが心配で……。今回の相談者さんもその一人です。中学3年生のお子さんから、進路を公立からレベルの高い私立の高校に変更したいと言われて当惑しています。
果たして教育費は足りるのか、子どもは勉強についていけるのか、親として何を準備すればいいのか。不安が尽きない相談者さんに黒田先生がずばりアドバイスします。
【相談】
来年中学3年生になる子どもを持つ40歳の母親です。ずっと公立高校に行くものだと思っていたら、ここにきて子どもが突然、これまで希望していた公立校よりも数段レベルの高い私立の高校に行きたいと言い始めました。教育費は足りるのだろうか、そもそも子どもがその私立校に行ってついていけるのかと、心配と不安でいっぱいです。これからの1年、親としてできる準備は何なのか。学費を用意するためにどんなことをしたらいいのでしょう? 黒田先生にぜひ教えていただきたいです!(40歳・女性)
※当記事では、2023年11月時点の制度をご紹介しています。
進路変更の理由を確認してみて
進路を変更したいと突然お子さんに言われたら、それはびっくりしますよね。きっとお子さんなりの考えがあるのだとは思いますが、まずはどうして進路希望が変わったのかを確認してみませんか。必ず理由があるはずですから。
その理由が例えば、友達が行くからとか、ただ塾の先生に勧められたからとか、あるいは有名校だからといった内容なら、もう少し慎重に考えるよう伝えたいところ。ですが、希望の職業に就くためなど、将来のキャリアデザインを考えての変更だとすれば、親としてはしっかりバックアップしたいと思えますよね。まずはその確認からスタートしましょう。

文部科学省の「令和3年度子供の学習費調査」によれば、公立高校に進学した場合に必要な教育費は約51万円。一方、私立高校は約105万円。公立の2倍ちょっとかかります。51万円ぐらいであれば収入の範囲内でやりくりして用意できるかもしれませんが、さらに大きい金額となるとそうもいきません。差額をどう準備するかを考える必要があります。
また、私立大学の付属高校に進学した場合、そのままエスカレーター式にその大学に進学するケースもあるでしょう。逆に、その私立大学に進学するために、高校から入学することを選択しているケースも少なくありません。もし相談者さんのお子さんの希望する高校がそうならば、私立大学への進学を想定した準備も必須です。つまり、大学進学に必要な費用を貯めながら、高校の学費についても備えなければならないということです。
鍵を握る有益な情報の入手
では、高校だけでなく大学にも通わせると、どのぐらいのお金が必要なのか。ここで、大学入学までにかかるお金と入学後に必要なお金についても見ていきましょう。
大学入学費用を準備する場合、受験料や交通費・宿泊費、受験した全大学への納付金を含めて国公立だと平均67万円、私立文系の場合は平均81万円*かかります。入学後にかかる費用は国立大学が年間約103万円なのに対して、文系の私立大学は約152万円。これは初年度の費用ですから、子どもを大学に進学させると卒業までざっと500万円以上もの費用がかかるわけです。
*出典:日本政策金融公庫 令和3年度「教育費負担の実態調査結果」
大きな金額だからこそ、いまからしっかり準備をしましょう。
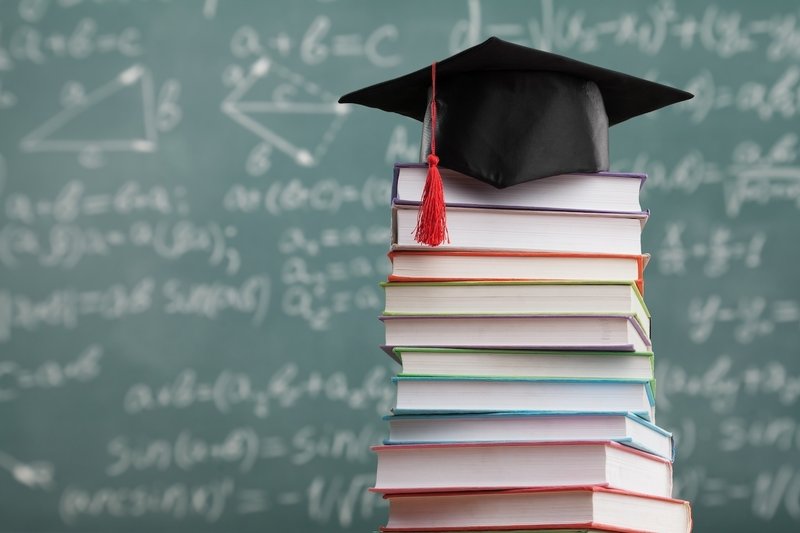
子どもの教育費は使う時期が決まっています。相談者さんの場合、お子さんの高校進学までに残された時間はあと1年。まずは希望する私立高校に進学するとしたらいくら必要で、いま現在いくら不足しているのかを試算して準備方法を検討します。
現実的な路線でいうと、貯蓄を取り崩して私立の進学費用にあて、大学の費用については中長期で考えていく必要があるでしょう。
教育資金設計の基本的な考え方は、①ためる・増やす、②借りる、③その他・親以外から援助を受ける の3つ。さらに、公的支援制度を活用するという選択肢もあります。
①の「ためる・増やす」は、時間の余裕がある場合に有効な方法です。今から大学進学に備えるのなら、積立貯蓄やつみたてNISAを活用するといいでしょう。
②の「借りる」方法は、奨学金と教育ローンの2つがあります。前者の奨学金は、給付型と貸与型の2種類に分かれます。奨学金といえば日本学生支援機構が代表格ですが、私立大学や自治体、企業が実施しているもの、〇〇財団や〇〇基金など公益法人が提供するものなどがたくさんあるのでチェックしてみてください。
なお、企業や自治体、財団などの給付型を申し込む場合は、高校3年生の9月~10月頃など申込の締め切りのタイミングが早いものもあるので注意しましょう。地方自治体の奨学金は日本学生支援機構のサイトで検索できます。
後者の教育ローンには、日本政策金融公庫や銀行などのものがあります。貸与型の奨学金は保護者が借りて学生が返済するのに対して、教育ローンは借りるのも返すのも保護者。貸与型奨学金は子どもの、教育ローンは保護者のこれからのライフプランに影響を与えます。貸与型奨学金を利用する場合には「卒業後に自分で返済していく意思があるかどうか」を、一度お子さんに確認しておく必要があるでしょう。
高校の授業料については無償化が進んでいます。国が行う「高等学校等就学支援金」は、2020年3月まで、一定の所得要件を満たす世帯に対して、公立高校の授業料は無料、私立高校は世帯年収によって授業料の一部が支給されるしくみでしたが、2020年4月からは、支給額が引き上げられ、私立高校に通う生徒への支援範囲が拡大されています。
また、各自治体が学費負担を軽減する「授業料軽減補助金」などの公的支援制度もあります。ただし、所得基準や計算方法、申請時の必要書類や提出期限についても自治体によってさまざまです。特に、自治体によって、対象となるのが県内の高校に進学した場合のみで、県外の高校に進学した場合は対象にならないとしているケースもあります。実際、高校の授業料は無料だと思って安心していた保護者の方が、県外の高校は対象外だと合格してから知って、驚いたという方もいらっしゃいました。
情報の有無が将来を左右するといっても過言ではありません。使える制度がないかどうか、受けられる要件についても、ぜひ積極的に調べてみてください。
子どもには家庭の経済事情を伝えるべき?
できるだけ子どもが望む学校に行かせてあげたい。不自由をさせたくない。これが親の心情だとは思いますが、経済的にどうしても厳しくて私立は難しい、というケースも考えられます。
その場合、私立を断念してもらうという選択肢もあるでしょう。また、ご家庭の経済事情をお子さんに正直に伝えるのも、私は「あり」だと思います。

もちろんこれは各ご家庭の方針や考え方次第。そういう話をお子さんにしたくないというご家庭も多いと思いますし、その気持ちもわかります。
でも、金銭的な現実を伝えることが必ずしも子どもに余計な負担を与えたり、負い目を感じたりさせてしまうわけではないでしょう。むしろモチベーションにつながるケースもあるはずです。
いまの時代、子どもを大学まで進学させるのは簡単なことではありません。大学進学のために必要な塾代も含めると、教育費は大きな出費になります。教育にはお金がかかる、という現実を子どもに伝えることは押し付けがましいことではないと思うのです。
相談者さんはいま40代ですから、あと約10年はお子さんのための資金が優先になるかもしれません。ちょっとシビアに言えば、子どもにお金をかけるということは自分の老後準備の開始がその分遅れるということです。そうした現実を客観的に受け止めながら、バランスを考えて準備を進めてくださいね。
<関連記事>
<クレジット>
取材/ライフネット生命公式note編集部
文/三田村蕗子
撮影/村上悦子
<プロフィール>
黒田尚子(くろだ・なおこ) 1969年富山生まれ。立命館大学卒業後、1992年(株)日本総合研究所に入社。1998年、独立系FPに転身。現在は、各種セミナーや講演・講座の講師、新聞・書籍・雑誌・ウェブサイトへの執筆、個人相談等で幅広く活躍。2009年12月に乳がんに罹患し、以来「メディカルファイナンス」を大テーマとし、病気に対する経済的備えの重要性を訴える活動も行っている。CFP® 1級ファイナンシャルプランニング技能士、CNJ認定 乳がん体験者コーディネーター、消費生活専門相談員資格を保有。
●黒田尚子FP オフィス
※こちらの記事は、ライフネット生命のオウンドメディアに過去掲載されていたものの再掲です。