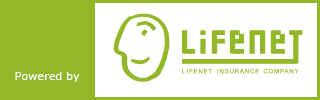羽子田礼秀(はねだゆきひで)さん(ハウス食品グループ本社アドバイザー) (撮影/横田達也)
■22年前、単身上海へ旅立つ
──羽子田(はねだ)さんは、日本のカレーをまったくゼロの状態から中国全土、台湾にも売ってこられた立役者でいらっしゃいますが、今年からハウス食品のアドバイザーに就任されました。久しぶりに帰って来られて、日本の印象はいかがですか。
羽子田:中国では毎日がエキサイティングでした。車に乗っていて、自分のほうの運転手は安全運転してても、いつぶつかって来られるかわからないし、絶えずビクビクしていました。いろんなところで交通事故を見ましたしね、それもひどい事故です。だから中国では車に乗っていて寝たことがないんですよ。
それと、中国に赴任している間、15年間は単身赴任でしたし、そういう意味では日本に帰ってきて、日本の良さを感じてますね。
──日本はどういうところが良いですか。
羽子田:ルールがあるし、やっぱり安心安全なんです。日本はとても安心安全な世界……食品を見ても新鮮で、「これは買っていいものかどうか」と迷うことがない。

アメリカの「カレーハウス」ビバリーヒルズ店で研修中の羽子田さん(1996年8月)
──羽子田さんが初めて上海に赴任されたのは1996年ですか?
羽子田:はい、42歳のときです。入社以来、大阪で9年間営業をして、それから東京の広域営業部で9年、合わせて18年間、営業一筋で来ました。中国畑でもないのに、突然、当時の社長に呼び出されて、行けと言われたんです。「米を食べる国は絶対、カレーが売れるはずだ。それを試したいんだ。だから羽子田、行ってくれないか」と。
当時、ハウス食品はアメリカで豆腐の工場をやっていました。シェアはアメリカでナンバー2かナンバー3で、年間10数億円ぐらいの売り上げ。それと「カレーハウス」という直営レストランを経営していました。今もありますが、リトルトーキョーから始まって、トーランス、ガーデナ……アメリカ西海岸専門です。
──ハウス食品が豆腐を作っていたとは知りませんでした。
羽子田:ハウス食品の海外事業は、アメリカの豆腐とカレーハウス中心という時代です。そこに中国に事務所を持つ日本の大手商社から、「豆腐スペックだけじゃなく、カレーを世界に広げていったらどうですか」とお誘いがあって、当時の社長が決断した。けれども、「いきなり中国でカレーを商売にするのは難しいだろう」ということで、一度、テストのためにカレーの店を上海で開くことにしたんです。
最初は3年間だけの約束だったんですよ。「3年経ったら、良くても悪くても店はやめるから、とにかく行ってくれ」と、それでお店の名前はアメリカと同じ「カレーハウス」で行こうということになって、単身、上海に旅立ったんです。
■中国初のカレーレストランをオープン
──上海ではどんなメニューを出されたんですか?

1997年、上海の花園ホテルの前という一等地に中国初の「カレーハウス」がオープンした
羽子田:カレーハウスのロゴはアメリカにあったものを使いましたが、メニューは中国人の嗜好を考えて変えました。私がレストラン運営を学んだビバリーヒルズのお店では、ご飯をお皿に盛り付けて、ポット入りのカレーをそれにかけて食べる。
けれども、上海ではワンプレートのほうがいいだろうと思いました。中国の人は揚げ物が大好きだし、ボリュームもないと駄目だから、カレーライスにとんかつを乗せちゃおう、コロッケを乗せちゃおう、カレーの横に赤い福神漬け、黄色いトウモロコシ、これは缶詰のスイートコーンですが、緑はブロッコリーを添えてとか。

上海カレーハウスの店頭ディスプレイ
──いろどりがきれいですね。
羽子田:中国人は色彩感覚が豊かなんですよ。1997年は中国の平均賃金が800元ぐらい、日本円にして約12,000円のときです。そのとき、うちのカレーが1皿42元です。対月給比で考えれば、日本円でカツカレーが5,000円ぐらいする感覚だったと思いますが、なぜ、こんなに高かったかのかというと、材料は全部、日本から輸入だったからです。
日本人は私一人しかいなかったし、 中国人がまったくカレーに馴染みがない以上、カレーを作れるコックはいないだろうと思いました。2キロ入りのレトルトソースを鍋で湯煎に掛けて、コロッケなんかはハンバーガー店で使っている冷凍食品用のフライヤーで揚げて、ご飯の上にパッと揚げ物をのせ、カレーをかけて、野菜のトッピングを添える。これだと味のばらつきがない。

上海カレーハウス店頭の「カレーメニューのサンプル」。「当時中国にシリコンで出来たメニューサンプルはほとんどなく、中国人のお客さまから本物か作りものか良く質問受けました」(羽子田さん)
「ルーを一から作った方が原価率が安くなるんじゃないか」という話もありましたが、社長の言葉どおり、これは中国人がカレーを好きかを調べるテストのための店なので、利益を出す必要がない。 僕の仕事は店長ではなく、総経理という役職でしたが、中国の人たちがどうやってカレーを食べるかを見ること、さらに、どのぐらいの頻度で来るか、子どもは来るか、お客さんは何を残したのか見る。
──何を残してたんですか。
羽子田:それが、何も残さなかったんですよ(笑)。子どもはペロペロ、お皿をなめてました。それと決して安い値段ではないのに、女性に結構来ていただいたんですよね。カレーハウスの上海店がオープンした1997年11月当時は、中国全土にマクドナルドとケンタッキーが50軒ぐらいしかなかったんですよ。今はケンタッキーだけで5,000店舗あります。マクドナルドは3,300店。
いわゆる洋食屋はあの時代、上海に1軒しかありませんでした。場所も花園ホテルの目の前……日本で言えば銀座・新宿ですね。今でも覚えていますが、203平米52席。楕円形の大きなテーブルも入れて、テーブルの真ん中に板を置いて仕切って、日本ではよくある一人席を作りました。
当時の中国には丸いテーブルしかなかったんです。大人数のときは、丸テーブルを2つとか4つくっつけて、という方法を中国で最初にやったレストランは、カレーハウスだったと思います。それまで中国では一人でご飯を食べる習慣がなかったのですが、1人で来ても、8人で来ても座れる、これが受けたんですね。

上海のカレーハウスのメニュー。アメリカではカレーのルーとライスは別にサーブしていたが、中国人の嗜好に合わせて、カレーライスと付け合わせの彩り野菜を一つのお皿に盛り付けるワンプレート形式を採用上海のカレーハウスのメニュー。アメリカではカレーのルーとライスは別にサーブしていたが、中国人の嗜好に合わせて、カレーライスと付け合わせの彩り野菜を一つのお皿に盛り付けるワンプレート形式を採用
■日本人は一人だけで寂しかった
──当時の上海には日本人もかなりいたんですか?
羽子田:当時上海に日本人は4,000人しかいませんでした。いまは5万5~6千人いますね。 単身赴任で毎日、うちの店に来ている日本人の方もいましたので、メニューはカレーだけにこだわらず、スパゲティも置きました。こうすれば、誰かを食事に誘って、「今日は私、カレー食べたくないの」と言われた時も、「カレーハウスにはスパゲティもあるよ」と言えば大丈夫でしょう?
社長命令で「きれいで清潔な店にしてほしい」と言われましたので、床はフローリング、建材をわざわざカナダから運んできて、トイレも日本のメーカーの洋式トイレにしました。店内は掃除も行き届いて、ウェイトレスはピンクとグリーンの二種類のエプロンを着せました。お客さんからは、「あのグリーンとピンクとではどちらが階級が上なのか」と聞かれて、「いや、あれは単に洗濯に出しているから、交互に着てるんだ」と説明しましたが、色の違いをそういうふうに取るんですね。

上海カレーハウスのスタッフと羽子田さん(前列右から2人目)。ウェイトレスのエプロンが色違いなのはおしゃれ感覚で、地位の違いはない
──女性たちが行きたくなるようなお洒落な雰囲気ですね。
羽子田:向こうの人たちはデートに誘うときに、自分が行って来た店の領収書を見せるんですよ。「こんなお店に行ってるんだよ」と相手に見せるために。それで総経理の僕もだいぶ領収書を書きました(笑)。経営状態は1年目は真っ赤っ赤で、資金が尽きそうでしたが、2年目からは黒字になってきました。
──羽子田さんは、お仕事は楽しかったんですか?

上海カレーハウスレストラン事務所(1998年)。この頃から、レストランが黒字に転じる
羽子田:いや楽しくなかった。僕は営業上がりですから、マーケティングや接客はしたことがない。石を持ってきて食べ物の中に入れられ、「ただにしろ」、と意地悪なことを言われたこともありました。
何より、寂しいじゃないですか、日本人は一人だけなんですから。1日のレストラン営業を終えて、お金を勘定して、ようやく家に帰って夜の10時半か11時。上海と日本では時差が1時間あるんですが、日本の本社の始業時間の9時に合わせて、朝8時には上海の事務所にちゃんと出勤して、昨日、あったこと──レストランでのトラブルや、役所に厳しい指導を受けたとか、全部日報に書いて、売上金額と一緒に東京にファックスで流すんです。
その作業を終えたら、レストランを開けるのが11時半。ランチの時間の始まりです。
──羽子田さんがお話しになると、何でも楽しい話のように聞こえますが、大変ですね。
羽子田:さすがに営業は、朝8時から夜の10時までぶっ通しではやりません(笑)。上海に行くとき、「日本国内はもう飽きただろう、もう18年も営業をやったから」と言われて旅立ちましたが、中国語ができないんです。期限は3年間と決まっていなかったら、とても続かなかったと思います。
レストランの立ち上げのとき、寺脇さんというカレーハウスの料理長が3か月だけ応援に来てくれて、レストランでの従業員指導をはじめ、一緒にお皿を買いに行ったり、厨房の造りを見てくれたりしました。
オープンから1か月半後に彼がアメリカに戻ってからは、本当の一人ぼっちです。インターネットのない時代──日本の本社との連絡は、固定電話とファックスだけ。あと日本から持って行ったのは、ワープロです。
いまは話せるようになりましたが、最初に行った時は、中国語は全然できませんでした。ニーハオ、シェイシェイ、サイチェンの3つだけ。当時の上海にはカラオケもなかったし、寂しいなんてもんじゃなかったですよ(笑)。
職場に日本人は一人だけだから、年に一度くらいしか帰れませんでしたし、1年ぐらいたった頃だったと思いますが、日本の家に電話して泣きました。「俺、もう寂しくて耐えられない」って(笑)。そしたら、うちの家内は教師をしていましたので、「我慢しないで、いつでも帰ってらっしゃい、子どもたちとあんたの一人ぐらいは食べさせるから」と言ってくれまして、「ならばもう少しがんばれるかな」と思って、続きました。
──かっこいい奥様ですね。

「カレーハウス」の看板を掲げたカレー店が上海に次々に現れたが、ハウス食品とは関係のない、いわゆる偽物!(1999年8月)
羽子田:いまでこそ中国のカラオケにも日本の曲が何百曲も入っていますけれどねえ。思い返せば、2001年に WTO (世界貿易機関)に中国が加盟してから、それを境に、ガラッと変わりました。レストランも含め、日本人の独資だけで店ができるようになりました。それまでは、中国の会社を巻き込まないと外国人はビジネスできませんでした。
ラーメン屋をはじめ、色々な日本のお店が中国でもビジネスできるようになってきました。いまでも覚えていますが、1999年の中国建国50周年の頃までは、まだ人民服を着ていた中国は、急速に発展していきました。
僕が入った1996年頃はボロボロの地下鉄の1号線が開通したばかりだったのですが、1999年の建国50周年(国慶節)に合わせて、文字どおりの突貫工事で、当時の国家主席の江沢民が飛行機も飛ばしました。
でも、21世紀に入るまではみんな貧しくて、中国社会では日本人の駐在員は一種のステータスでもあった時代でした。
■普通の人たちがお金を貯めて食べにきてくれた
──最初の約束では3年のはずが、羽子田さんの駐在期間は伸びて行くのですね?
羽子田:はい、3年で帰るはずだったんですけれども(笑)。上海のカレーハウスも3年で閉店するはずが、継続して営業することになりました。だんだん、日本の人気ビジネスニュース番組やドキュメンタリー番組、各種経済新聞にも、「ハウス食品の先進的な中国での取り組み」として取り上げられるようになり、注目を集めはじめた。中国のお客さまもついていることだし、「もうちょっと続けようじゃないか」という話になりました。そのときはすでに僕は、台湾を担当していましたが。
ただ、ハウス食品の本職はレストラン業ではありませんから、おのずと限界もあったのは確かです。ルーはレトルトを湯煎にかけて提供していたため、日本のレストランに比べて「カレーがぬるい」と、日本からのお客さまによく指摘されました。鍋でグツグツ煮ないと、どうしても皿を出すとき冷めちゃうんですよ。
いろいろ辛いことも多かったけれど、カレーハウスはいわゆる富裕層のお客さんだけでなく、中国の若い人たちが、他の日はうどんや饅頭を食べて、お金を貯めて、うちの店にカレーを食べに来てくれたことは忘れられません。警察官が制服を着たまま、食べに来たこともありました。制服を着たまま、勤務時間内に来るなんて、ちょっとありえないと思うんですが(笑)。
──「晴れの日はカレーハウスで洋食を食べる」という文化を作られたということですね。
羽子田:はい、ワインも出しましたし、ランチからディナーの間は喫茶店メニューも開発して、フルーチェを使ったパフェも作りました。グリコさんのポッキーを使って、アイスクリームと、そこにフルーチェの業務用も入れて……やがて、カレーライスが認知されだした頃、上海の道を歩いていたら、ふと看板に「カレーハウス」という店があるんです。5店舗ぐらい。ただ、これはうちの支店ではなくて、要するに真似されたんですね(笑)。
──カレーハウスでの経験を踏まえて、羽子田さんの次の冒険はどこへ向かうのでしょうか?
羽子田:3年後、台湾の担当を終えて、上海に戻ることになります。今度はいよいよ、日本のバーモントカレーを中国で売るという使命のために。
──ありがとうございます。続きは次回、お聞きすることにいたしましょう。

羽子田礼秀さん(撮影:横田達也)
<プロフィール>
羽子田礼秀(はねだ・ゆきひで)
1954年東京都生まれ。中央大学経済学部卒業。78年ハウス食品工業(株)に入社。大阪・東京本社で18年間、営業を担当した後、96年カレービジネス起ち上げのため、上海に駐在開始。2009年上海ハウス食品社長、17年ハウス食品(中国)投資公司最高顧問などを経て、18年より現職
●ハウス食品グループ本社
<クレジット>
取材・文/樋渡優子
インタビュー撮影/横田達也
写真提供/ハウス食品グループ本社株式会社