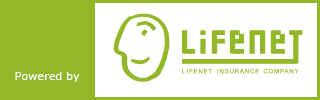分身ロボットOriHime。下から見上げる顔は猫をイメージさせる
誰でも人から必要とされ、自分の居場所が見つけられる社会を実現したい──。オリィ研究所・所長の吉藤オリィさんは“人の分身になる”というコンセプトのロボットを開発することで、そんな夢を実現しようとしています。
吉藤さんが開発しているのは、手のひらサイズの遠隔操作ロボット「OriHime」。スマートフォンやタブレット端末、PCから遠隔操作することで、首や腕を動かしたり、会話することができます。そうすることで、病気やケガで寝たきりになっている人でも、このOriHimeを持って行ってもらうと、会社の会議に参加したり、旅行に一緒に行ったりできるようになるのです。
つまり、人の代わりになるロボットではなく、人と人をつなぐためのロボット。吉藤さんはOriHimeにより、「カラダが動かせない人でも社会参加できる」ようにすることで、「孤独を解消する」ことを目指していると言います。
幼少期から周囲に馴染めず、小・中学生のときには3年半の不登校を経験。そんな中でも“ものづくり”に生きがいを見出し、今ではOriHimeによって、多くの人に生きる希望を与えている吉藤さんのモチベーションとは何か。お話をうかがいました。
■画期的な車いすを開発
──吉藤さんは著書の『「孤独」は消せる。』(サンマーク出版)の中で、自身のロボット開発の背景には不登校の経験があると明かされています。
吉藤:最初は病気がきっかけでしたが、長く休んだことで、学校に行きづらくなってしまったんです。地方の小さな町の出身でしたから、外に出ようと思っても、「あいつは元気になってもサボっている」と周囲の目が気になってしまう。そのうち自分自身でも「僕はダメなやつだ」という自己否定をするようになって、小学校の高学年から中学生のほとんどを不登校で過ごしました。

トレードマークの「黒い白衣」を着た吉藤オリィさん
──そこから再び学校に通うようになったのは?
吉藤:以前からものづくりは好きだったことから、母親がロボットコンテストへの参加を勧めてくれて。このときに出会ったロボット開発もする先生にあこがれ、その先生がいる工業高校へ弟子にしてもらうつもりで進学することにしたんです。
──その高校時代に開発されたのが、ジャイロセンサにより傾きを感知し、自動で補正する画期的な「電動車いすWander」ですね。
私の車椅子いじり歴はもう14年になる。
昨年、取材で母校の王寺工業高校を訪問したら仲間らと作っていた電動車椅子が展示されていて、ジャイロセンサにより傾きを感知し補正する水平制御機構がまだ動作して感動した。https://t.co/4P85yQGHsi pic.twitter.com/gQt9nNGkOG— 吉藤オリィ@新著書「サイボーグ時代」1.22日発売 (@origamicat) January 7, 2018
吉藤さんのTwitterより。過去に製作した電動車椅子
──この車いすで吉藤さんは「JSEC(ジャパン・サイエンス&エンジニアリング・チャレンジ)」で優勝し、アメリカで開催された世界最大の科学コンテストでも3位に入賞されました。なぜ、車いすを開発しようと?
吉藤:私は不登校だったから、人に迷惑をかける側の人間だったわけですね。肩身の狭い思いをしている両親に対して「ありがとうございます」と「ごめんなさい」を繰り返す日々で、そうすると最後は負い目で何も言えなくなるんです。それでどんどん孤独になっていく。だから、工業高校に入ったときには「何か人の役に立つものを作りたい」と考えていました。
そんなとき特別支援学校のボランティアに参加して。体が不自由だったり、知的なハンディキャップがある生徒たちが車いすに乗っていたんですが、それを押してみると、あまりに不便で衝撃を受けました。これを解決したいというのが、最初のモチベーションでした。
──吉藤さんは今でも「視線で操作できる車いす」や「Nintendo Switchで操作できる車いす」など、継続的に車いすの開発に取り組んでいますね。
昔、車椅子をいじっていた時、当事者ではない人から「車椅子で遊ぶなんてけしからん!」と怒られた
そう思うのは勝手だが、私は車椅子を特別なものだと全く思ってないので、バイクや車をいじるように改造する。視線で操作できたら便利だし私のデスクはこれでいいと思ってる。
もっと皆乗ればいいのに pic.twitter.com/KYgrMKwzFX— 吉藤オリィ@新著書「サイボーグ時代」1.22日発売 (@origamicat) January 6, 2018
吉藤:私は車いすは福祉機器として完成度は高くないと思っていて。たとえば、メガネってありますよね。メガネは完成度の高い福祉機器です。目が見えないって障害じゃないですか。でも、メガネをかけている人を障害者とは言いません。そのくらい生活に溶け込んでいる。しかし、車いすは障害者のものっていうイメージが根強くあります。
私自身が小学生で入院したとき、車いすに乗ったんです。その瞬間、車いすで運んでもらうのが申し訳なくなったんですよ。人に迷惑をかけている感じがして、めちゃくちゃ恥ずかしかった。それ以来、車いすの人は常にこういう思いをしているのかなって気持ちがずっとあって。

私は車いすを一人乗りのオープンカーだと思っているんですよ。だから自分一人で動かせるようにしていきたいし、もっと気軽にいろんな人が利用できるようにしていきたい。車いすを便利にすると同時に、その社会的なイメージを変えることで、車いすに乗っているときに感じる申し訳なさをなくしていきたいと思っています。
■人工知能では孤独を解消することはできない
吉藤:いきなりロボットを作り始めたわけではなくて、もともとは高専に進学して人工知能の研究をしていました。車いすの開発で賞をもらい、ものづくりを続けていきたいと思ったときに、自分がずっと感じてきた孤独を世の中から解消するために人生を費やそうと決めたんです。
それで人は話し相手がいなくて孤独になるのだったら、人工知能で話し相手を作ればいいと思った。でも、研究を続けるうちに、「これが孤独の解消になるのだろうか?」という疑問が出てきました。
──どういうことですか?
吉藤:自分がどうして不登校から社会復帰できたかと考えたときに、私の場合は人との関わりがきっかけだったんですね。母親にロボットコンテストの出場を勧められたり、ものづくりの師匠との出会いだったり、ボランティアの経験だったり。人との交流の中から自分の役割を見つけて、そこから社会復帰してきた。

人間社会は良いことも悪いことも、思い通りにいかないことがいっぱいあるじゃないですか。そこで自分の思い通りの人工知能を作ってしまったとすると、居心地が良くなってしまって、人間社会に居場所を見つける必要性を感じないんじゃないか。人間社会に戻れなくなるんじゃないかと思いました。
それに技術的にも、人間らしく見える人工知能の開発にはまだまだ課題があることがわかり、「人工知能で孤独を根本的に解消することはできない」という思いを持ったんです。
──それで高専を1年で退学し、早稲田大学の理工学部に入学されました。同学部は「ワボット」と呼ばれるほどロボット研究で有名ですが、いつ頃からOriHimeの開発イメージを持つように?
吉藤:入学した直後は、また具体的に何をしたらいいのかわからなくなっていました。「孤独の解消には人との関わりが欠かせない」という確信があったのに、肝心の私自身が「対人コミュニケーションの非ネイティブ」だった。友達もいないし、そもそも「友達ってコスパが悪いよな」って考えて人工知能の研究をしていました(笑)。
だから、「人間にとってコミュニケーションとは何か?」ということを学ばなければ、どんなロボットを開発すべきなのかもわからない。それでコミュニケーションネイティブの人たちとの“異文化交流”をしようと思って、いろんなサークルに入りまくりました。
■コミュニケーションとはリアクション
──大学ではどんなサークルに?
吉藤:社交性をインストールするために社交ダンス部に入って、「あ、これは違う」って思ったり(笑)、映画や演劇のサークルに入って、舞台の演出やドラマの作り方について学んだりしました。
特に演劇は役に立ちました。台本とかめちゃくちゃ読みましたね。私はコミュニケーションの非ネイティブだから、こういう話し方をすると他人から好かれるんだなって、ネイティブのみんなが意識せずにやっていることに法則性があることに気がつくんですよ。
たとえば、コミュニケーションはリアクションなんです。内心は何が面白いかわからなくても、「マジかよ!」ってわざと大げさにリアクションする。そうすると相手も楽しくなって、自分も楽しくなってきます。「他人は自分を映す鏡」と言いますが、あれって本当なんですよ。自分が楽しい人間として振る舞えば相手も楽しくなるし、自分が厳しく振る舞えば相手も厳しくなる。

思えば、私が学校に居場所がないと感じたのも、久しぶりに学校に行って、「おはよう」って挨拶しても誰も返してくれないことが辛かったからです。透明人間になってしまったような気分になりました。リアクションがないとコミュニケーションが生まれず、「ここに自分の居場所はない」と感じるんですね。
そこから不登校の人や入院中の人が、家や病院にいながらも仲間とコミュニケーションができる「分身ロボット」を作りたいと思いました。たとえ寝たきりでもロボットを通じてリアクションのやり取りがあり、コミュニケーションが発生すれば、「そこに自分の居場所がある」と実感することができるからです。
──しかし、それなら人間に似せたデザインのロボットを作ろうとは思わなかったのですか?
吉藤:人間そっくりに作れば命が宿っていると思えるかというと、必ずしもそうではないと考えたんです。スーパーコンピューターでも命が宿っているように思える人工知能は作れないのに、小さな子どもは自分が大切にしているクマのぬいぐるみに命があるように思うじゃないですか。あるいは、私たちは人形劇に感情移入して泣いてしまったりする。
つまり、“人間らしさ”とは客観的に人間に似ているかどうかではなく、見ている人がどう思うかにかかっています。そして、それは演出で作れるのです。それこそパントマイムであれば、ここに壁があるように見せることができます(と実際にやってみせる)。
──すごい上手ですね!
吉藤:自分のカラダの動きを知らない人間がロボットの動きを作れるはずがないと思って、大学時代にパントマイムを習いました。これって催眠術でもなんでもなくて、私が「壁があるように思わせる動き方」を知っているからできるわけです。これと同じように、「人間らしく見える動き方」というのがわかっていれば、周りの人が勝手にロボットに“人間らしさ”を感じてくれます。
オリィ研究所6周年記念として、これまでの研究成果を展示するオリィフェスが開催される
──OriHimeの“顔”は能面を参考にされたとのことですが、それも同じ理由から?
吉藤:そうです。能面は演出によって観客が喜怒哀楽を勝手に解釈します。顔のデザインはこのくらい抽象的なほうが、「まるで笑っているみたい」とか「まるで泣いているみたい」という解釈の余地が生まれるんですよ。
■研究室がないなら自分で作るしかない
──そういう研究って、大学で教えられたものだったんですか?
吉藤:いえ。ほとんどは理論数学や物理をやることでロボットを制御していこうという研究室でした。演劇的な方法論をロボティクスに応用すればいいと考えている人はいなくて。だから、3年生になっても入りたい研究室がなくて困るわけですよ。
それで「大学にないなら自分で作るしかないよな」と思って立ち上げたのが、当時住んでいたアパートに一人で作った「オリィ研究室」でした。
──それが現在のオリィ研究所につながっていくわけですね。そこから吉藤さんはOriHimeを開発し、多くの人の孤独の解消に貢献されています。
吉藤:OriHimeは寝たきりの人だけでなく、会社のテレワークにも活用されています。それまではSkypeを使ってテレビチャットをしていた人が、OriHimeを会社で使うことで、「会社に居場所を感じられるようになった」と言ってくれました。
単に会議をするだけなら、Skypeだけで十分なんですよ。でも、会社の人の発言に対して、その場でOriHimeでリアクションをすることで、職場の中に“その人がいる”ような感覚が生まれます。そうすることで、離れていても会社に居場所ができていく。
OriHimeによって帰属意識を感じられる場所が作れるのであれば、もしカラダが不自由になっても働き続ける希望が生まれますよね。「ロボットによって孤独を解消する」というのは、こういうことだと思うんです。
<プロフィール>
吉藤オリィ(よしふじ・おりぃ) オリィ研究所 代表取締役所長、ロボットコミュニケーター。1987年生まれ。奈良県出身。高校時代に電動車いすの新機能を開発、国内最大の科学技術フェア「JSEC」で優勝。インテルが主催する世界最大の科学大会「ISEF」で入賞を果たす。早稲田大学在学中にオリィ研究所を立ち上げ、孤独を解消するロボット「OriHime」を開発。AERA「日本を突破する100人」、米フォーブス誌「30 under 30 2016 ASIA 」に選出。著書『「孤独」は消せる。』(サンマーク出版)
<クレジット>
取材・文/小山田裕哉
撮影/村上悦子