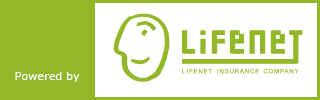「先生は、飲みたいんだったら、治療中も飲んで構わないっておっしゃってたんですよ。がんだからお酒はダメということではなく、泥酔して転んだりつまずいたりすることは必ず避けるべし、と。僕の場合、片脚が不自由だから転ぶのが一番まずいんです」
相手に余計な気遣いをさせない、という印象のその人は、それまで何度も会ったことがあるかのように、自然と会話を始めた。座っていればその左脚が不自由であることはわからないし、後方に置かれた松葉づえにも気が付かない。まして、彼ががんを経験した人などということは想像にも至らない。ただ、その語り口が面白くて魅力的で、このまま一杯どうですか、なんて言いたくなる、そんな人なのである。
「みんな、がんと聞くとお酒は飲めないと思うみたいですね。退院後に友人がごはんに誘ってくれましたが、いつもなら飲みに行こうというその人が選んだのは、巣鴨のショートケーキ屋さん(笑)。おいしかったです」
青山さん(30代 仮名)は、2018年に希少がんの一種である左大腿悪性軟部腫瘍・粘液型脂肪肉腫と診断された。そのときすでにステージ3。抗がん剤による術前の化学療法を経て、広範切除と人工関節置換の手術を経験。術後にまた抗がん剤治療をし、半年にわたる治療を終えて、職場に復帰をした。
がんのこと、障がいのこと、なんでも話しますよと言ってくれたのをいいことに、彼に根掘り葉掘り聞いてみた。そのインタビューの前編をお届けする。

■悪性でした、入院してください、会社休んでください
「2017年の10月に左の大腿四頭筋が痛くて病院へ行きました。曲げると痛かったんです。先生に“君も歳だね、痛み止めを出すよ”と言われたんですけど、痛みは治まらない。そうこうしているうちに年末になって、帰省のため乗った飛行機で痛くて座っていられなかったんです。これは仕事にも支障が出るからいかん、と思って再度受診。そうしたら“MRI取りましょう”となったんです。めちゃくちゃ命拾いだったなと今なら思います。
MRIの結果は、“血腫か腫瘍だとしても基本は良性だと思うけど、念のため、大きな病院を紹介しますね”、ということでした。そしたら翌日に電話がかかってきて、“放射線科の先生に診てもらったらやばい影が出てるかも、と。予約を取りなおしてでもすぐに紹介した病院に行ってください”ということでした」
──急いで病院へ、と言われたとき、どういう心境だったんですか?
「自分でもよくわからないんですけど、特になんとも……。もともと予約は2週間先だったんですけど、相談したら2、3日後くらいに早まって。言ったら早くなるものなんだなと思った程度。紹介された病院ですぐ生体検査をしたんですけど検査結果が出るまで、普通にお酒を飲んでいました。
知り合いには“俺、超かわいそうじゃん、絶対がんだよ、絶対悪性だよ~”って言って飲んでいました(笑)。家でも泣かなかったし、そのときは自分でなんの病気だろうかと調べたりもしなかった。どうせ良性だと思っていたし。死ぬ~死ぬ~って大騒ぎして(笑)、周りの反応も覚えてない。
生検の際に“結果は2週間後です”と言われたんですけど、実際は1週間でしたね。仕事中に病院っぽい番号から着信があって、その次に母親からも着信がありました。そのときは少しショックだったかも。ああこれはマズイな……、と。僕はそういう知り方をしたんですよね、病院と母からの着信で、ああダメだったんだな、と。
母に電話をしたら案の定、僕より先に先生から連絡を受けていたようで、取り乱していました。それで自分が冷静になったんです、“大丈夫、これから病院に行ってきます”と。それから病院に電話したら、結果が良くないので何時でもいいから来てください、と言われました。それが2018年の1月末です。
さすがにその日は上長に言いましたね、“ちょっとダメだったっぽいんで、病院に行きますし、明日以降は仕事しません”みたいな。もうちょっと丁寧に言ったかな(笑)。病院に行ったら、すぐでした。“悪性でした、入院してください、会社休んでください”……あっという間に進みました」

■がんらしいんですよ、あははは
──職場に言うのはすごくハードルが高いという人が多いですが、すぐお伝えしたんですね。普段からコミュニケーションをちゃんとしてても、自分ががんかどうかを言うのは別かなと思うところがあって。何を以てその場で休みますとか、がんですって言えたのか、気になります。
「上長には日ごろからプライベートなことも話していましたね。それまでにも病院に行くのに仕事を抜けたりもしてましたし、移動中のタクシーの中で、“生検ってまじやばかったんですけど”とかそういう会話もしていました。“僕、正直ダメかもしれません”とかいう冗談も言ってたんですよ。上長に話すことと、飲み屋で話してることが一緒だけど(笑)。
僕の場合ですが生体検査はめちゃくちゃ痛かったんです。金串のようなものを大腿部に刺して筋肉組織を取るんですけど、一週間くらいは脚を引きずってました、痛くて。だから、会社でも“どうしたんだ”と聞かれて、“いや~、がんらしいんですよ、あははは”なんて言って。
上長からは、“いい会社なんだからここから先は絶対にしがみつけ。病気と介護に手厚い、いざというときに頼りになる会社だから”と。福利厚生が充実している会社だと言われても、特に実感なく過ごしていましたし、それを目当てに入社したわけではないですけど、偶然、本当に良かったです。
ただ、仕事という意味では、自分の中でも一番のモチベーションというかご褒美的に考えていた仕事があったんですけど、それができないというのは、“そうか……”となりましたね。海外に行く仕事だったんですけど、病院の先生に聞いたら“絶対ダメです”と言われて。そこで、“全部捨てないとダメなんだな”と実感しました」
──全部捨てる、というのは重いですね。
「でも、終わってみると、すぐ休んでよかったなと思います(笑)。僕の場合は、がんと脚の障がいで1年くらい会社を休みました。そういう環境に身を置くと、いかに自分がこだわっていた仕事とか東京で働くとか、そういうのが些末なことだったというのがわかるというか。
リハビリ病院に行って、“来週いつ空いてます?”と言われて、“病気なんだからいつでも空いてますよ”というようなやり取りを普通にするわけですよね。それまでのことが全然大したことなかったんだなと思います。がんサバイバーでも、みなさん再就職されているし、今の自分の環境が絶対じゃないんだなと思いました」
■障がいに偏見を持っていた自分に気づくことができた
「リハビリをしているときの話なんですけど。自分が筋トレやリハビリをしている横をまったく動けない人が通っていくんですよね。お母さんが車いすを押してプールに連れていってあげて、療法士さんがプールに入れてあげて。入れるというより身を水につけると言う方が近いですね、そしてその人は“ああああー”と声を出している。
あるときは、パラリンピック選手のような人がJAPANと書いてある水着でハードに泳いでいるんですけど、僕はその横で、脳こうそくのおじいさんと競争していたりするわけです。
自分はそこまで障がいのある方に偏見があるほうではないと思っていたけど、でもやっぱり昔は、ダウン症の子がいると“うわっ”て思うような感じでした。でも今は“ダウン症なんだね”くらいの感覚に変わりました。あの子たちって必ずおはようとか言ってくる、それがすごく新鮮。最初は恥ずかしくて返せなかったけど、あいさつしないの僕くらいなんですよ(笑)。だから、ちゃんと返すようになりました。
おまえのその赤いスマホどこで買ったの? と、毎日聞いてくる自閉症と思われる子もいましたね。“いや、だから、お店だって”って毎度答える(笑)。でもまた、“いくらなのいくらなの、僕もほしい”って言うから、“昨日も言ったけど、あげられないし、いくらなのかも覚えてないよ”って返す…… みたいなことをやってると、自分が偏見をもっていたんだなと思うし、新鮮だった。病気してよかった、というのは言いすぎですけど、それでもこの歳で実感を持って自分が変われたので非常に良い機会になりました」

■泣いたのは2回だけ、人とのかかわりの中で
──がんの治療中、生活はどうされていたんですか?
「地方出身なので母が東京に出てきました。先生に聞いた話ですけど、自活で乗り越えた人は一組しか知らない、と。その人も都度親が出てきてサポートされていたそうです。なので、自分は嫌でしたけど、母と暮らすことになりました。
僕が涙を流したのは2回だけ。母と一緒に暮らすことになり、それまでの部屋を引き上げるときの退去の立ち合いで、空っぽになった部屋を見て。僕は新宿が好きで新宿に住んでいて、そこから離れたところに引っ越したんですけど、退去の帰りに泣きました。今もその時のことを思い出すと、ぐっと来ますね。自分なりにがんばってきたものが……。賃貸だったけど、自分の家だった気がして。
もう1回泣いたのは、会社のみなさんから手紙をもらったときですね。後輩で、僕が送ったメールを印刷してこのとき私はこう思ったみたいなことをまとめてくれた子がいたんですけど、それで泣きました。病気がうんぬんというより、人がいて、相手がいて、という人とのかかわりのところで悲しくなったんですよね」
──がんだとわかって、何が一番頭の中を占めていましたか。お金のこととか、本当に治るのかなとか、この先どうなるのかなとか、何を一番不安に思うのかなと。
「なんの心配をしていたかなあ。お金という面では、医療費控除の申請をするときに計算したら、医療費としてかかったのは180万円くらいでした。治療費以外にも引っ越し、両親の移動費等ありましたら出費はかさんだわけですけど、会社の福利厚生や給与継続に大変助けられました。がん保険は両親が自分にかけていてくれていたのがあったんですけど、僕の口座には入ってないな……(笑)。
実は僕に高額療養費制度のことを教えてくれたのはタクシーの運転手さんなんです。検査結果を聞いた日の帰り、今日は贅沢してタクシーで帰ろうと思ったんですね。そして、病院から乗ったタクシーの中で、会社に電話をしました。
伝えたら電話を受けた女性の先輩が泣いてしまって。いきなり泣き出したんで僕は笑っちゃったんですけどね、“早い早い(笑)”って。会社にはほぼ行けないわけなので、電話で遠隔でサポートしてくださいって伝えました。その電話のあとでタクシーの運転手さんが“高額療養費の話出た?”って聞いてくれたんです。月8万ちょいくらいに上限が抑えられるんだよ、と。
その方は、奥様を乳がんで亡くされたということだったんですが、病院ですごく良くしていただいたから、僕はあの病院でお客さまを乗せることにしているんです、というお話でした。あの運転手さんには感謝ですし、僕以外にも他にも助けられている人がたくさんいるんだろうなと思います」
──実際に治療が始まっても不安はなかったですか?
「病気の不安が出てきたのは治療が始まってからですね。競泳の選手が“思っていたより数千倍つらい”とツイートしていましたが、あの気持ちはすごくわかります。
がんは珍しい病気ではないという時代だし、抗がん剤も一般的な治療というイメージがあったんですけど、みんなこんなにきついことを経験してるのか? こんなに抗がん剤ってつらいのか? と思いました。副作用がきつかったですね。
看護師さんによると、副作用がまったくない人もいるらしいですが、僕は、一日だけでしたけど、向精神薬が処方されたくらい精神的にぶれたことがあって。どうしても点滴を抜きたい衝動に駆られたんですよね。先生に相談したら“いい薬がある”ということで、処方されたものを飲みました。これがめちゃくちゃ効きました(笑)」
──痛いというより、きついんですね。
「そうですね。でも抗がん剤が終わった後、手術をしたんですが、それはむちゃくちゃ痛かったです。今でこそひょいひょいしてますけど、左脚を地面につけた時点で激痛が走るんです。それが最初の1か月続きました。説明しようもない痛みがありましたね。入院中、ひざを曲げ伸ばしするマシーンが備え付けられていてリハビリ的にやってましたけど、相当痛かった。今もひざは90度くらいしか曲がらないですけど、いまだにたまに痛みます」

■先生だったらどうしますか?を聞く
──ステージ3と言われて、具体的な治療方針というのはその場で説明があったんですか?
「最初のほうに、“おそらく切断はしなくてよいでしょう、ただ、骨は取ります”と言われました。“転移のことを考えるとつながっている部分は骨だし、浸潤しているとまずいから骨は取ります、ひざは開けてみないとわからないから、残すかどうかはわかりません。抗がん剤は全部で5回、1週間やって2週間あけて、を2回か3回やってから手術します。手術のあとに残りの抗がん剤をやります”と説明がありました。
たまたま職場にいた医師免許を持った人と、知り合いのおじさんで医学部を出た人がいたので聞いてみたんですよね、“この治療はどうですか?”と。そしたら2人とも“そのままやりなさい”と。もう一人、医療に知見のある人に聞いたらその人も“そのままやりなさい”ということで、偶然周りにいた医療系の人が3人ともOKと言ったので、先生の言うとおりにしました。
両親は、地元に転院させるとか言ってたんですけど、僕はお見舞いに誰も来ないのも嫌だし、むしろみんなに来てほしいし、お見舞いの品もお金もたくさんほしいから、嫌です、と(笑)」
──標準治療を選択するにあたってのセカンドオピニオンやサードオピニオンを聞いてみるというのを自然にやられてたんですね。判断に迷うことはなかったですか?
「“先生だったらどうしますか”というのを折に触れて聞いていたんですよね。“先生は標準治療以外の食べ物での療法とかあったらどうします?”とか聞きましたよ(笑)。先生は“ないです、標準治療だけやってもらいます”と。“ほんとに?? ほんとに?”と聞いても“標準治療だけ”。
アメリカの国立がん研究センターが、がんの予防ににんにくがいいって言ってますけど! と聞けば、“ガーリックがいいと思うなら召し上がってください”。ブドウジュースが良いって何かに書いてありましたけど! “ブドウジュースがいいと思うなら飲んでください”と、そういうやり取り(笑)。
実は、手術をしないという選択肢もゼロではなかったですが、“先生だったら手術します?”“100パーセントします”“じゃあ手術してください”という感じで決めました。なので、ことあるタイミングで先生には先生だったらどうするかを聞いていましたね。
先生とはすごくフラットな関係でした。この間も定期検査のときにお会いして、“転勤になったので次に来るときはいません”とサラッと言われて。えっ!? 最後にそれだけ? と思いましたけど、僕にはその距離感が合っていた。
その先生に限らず、腫瘍を扱っている先生は腫瘍が取れたら僕に興味がなさそうだし(笑)、リハビリの先生はリハビリの先生で、“来週病院に行くんですよ”と言っても“そうなんだ、何の検査をするの”と。僕はすごく怖いわけですよね、また再発していたらどうしようとか不安なんですがリハビリの先生にはそれはたぶん伝わってなくて。“僕が担当してからさらに(ひざが)曲がるようになったから病院の先生がほめてくれるといいな”とか言ってましたよ。いや、そこじゃないよね、と(笑)」
──(笑)。ネットで検索は全くしなかったんですか?
「食べ物だけは検索して、信じて食べてましたけど、病気に関しては見なくなりました。僕の病気のことを調べると論文が出てくるんですけど、難しくてよくわからないし、調べたところで悪性度が下がるわけでもないし。僕みたいに治療が終わったからって、酒飲んでラーメン食ってるやつは、いずれにしても早く死ぬんだなって(笑)。
とはいえ、にんにくはかなり食べましたよ(笑)。当時は母と暮らしていたので、おんぶに抱っこで、買い物に行って高価なにんにくとか“にんにく食べるとがんが消えるらしいから~~”って、かごに入れてました(笑)」
──青山さんの話を聞いていると、もし自分ががんになったら、青山さんのようにありたいと強く思います。にんにくを食べるかどうかはわかりませんが(笑)。
<クレジット>
取材・文/ライフネットジャーナル オンライン 編集部
撮影/横田達也